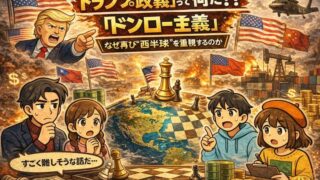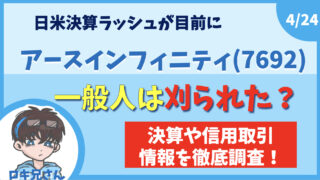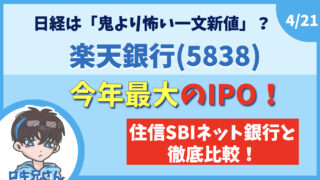目次
江戸の商人に学ぶ!そろばんと信用の「お金教育」
こんにちは、『えすふぁみ☆家族で株投資』です。
土曜日は「子どもとお金」をテーマにお届けしています。
今回は、今からおよそ200年前——江戸時代の商人たちが実践していた「お金の教育」に注目してみましょう。
学校も教科書もなかった時代、それでも日本の商人は世界でもまれに見るほど“金融リテラシー”が高かったと言われています。
その秘密は、家庭や家業の中にあった「実践型の学び」にありました。
1. 江戸時代の商人教育:寺子屋と家業が教室だった
江戸時代の子どもたちは、寺子屋や商家で“実務を通じて”お金の扱いを学びました。
寺子屋では、読み書きそろばんが教育の三本柱。
中でも「塵劫記(じんこうき)」という算術書は当時のベストセラーで、そろばんの使い方や利息計算、取引の方法などが詳しく書かれていました。
子どもたちはそろばんを弾きながら、「お金の動き」を数字で理解していきました。
お金を“抽象的なもの”ではなく、“自分の手の中で動く現実”として体験的に学んでいたのです。
2. 家業で育つ「実践の金融教育」
商人の家庭では、子どもは遊んでばかりではいられません。
朝から店先を掃除し、帳簿をつけ、仕入れを手伝い、在庫を数え——
その一つひとつが「お金の流れ」を理解する実地訓練でした。
日々のやりとりを通じて、子どもたちは自然に「利益の出し方」「信用の大切さ」「取引先との関係づくり」を学んでいきました。
お金だけでなく、「誠実さ」や「人との約束を守ること」が商人の基礎であり、それが信用という“見えない資産”を生むと教えられたのです。
3. 「信用」と「長期的な視点」を重んじる文化
商人教育の中で最も重視されたのが、「信用」と「長期的な商いの視点」でした。
江戸時代のことわざに、
「売り手よし、買い手よし、世間よし」
という“三方よし”があります。
これは近江商人が伝えた理念で、
売る人(自分)も満足し、
買う人(お客様)も喜び、
世間(社会)も潤う
という三つのバランスを大切にする考え方です。
子どもたちは商売の中で、お金を“自分のため”だけに使うのではなく、“社会の循環の一部”として考える習慣を身につけていきました。
4. 明治時代の近代化と“学校で学ぶ金融教育”
明治維新後、日本は急速に近代化します。
それまで家業中心だった金融教育が、学校教育として体系化されました。
福沢諭吉が西洋の「複式簿記」を紹介し、商業学校が次々と設立されます。
帳簿や会計を「科学的に学ぶ」仕組みが広まり、商人教育は社会全体に広がっていきました。
この時代に活躍したのが、実業家・渋沢栄一です。
彼は『論語と算盤(そろばん)』で、「道徳と経済を両立させる」ことの重要性を説きました。
つまり、「お金を稼ぐ力」だけでなく「お金を正しく使う力」 が、本当の“金融教育”だと説いたのです。
5. 商人の金融教育が現代に残した教え
昔の商人教育には、今の時代にも通じる大切な教訓があります。
実践で学ぶこと:帳簿や在庫管理の中に“生きた算数”がある
信用を重んじること:お金は信頼の上に成り立つ
長期的な視点を持つこと:利益だけでなく、持続する関係を築く
家族で学ぶこと:家庭が最初の金融教室
まとめ|“そろばん”に込められた知恵
江戸の商人たちは、そろばん一つで世界を見ていました。
計算の正確さだけでなく、「数字の裏にある意味」や「人との信頼」を重んじる文化が、そこにはありました。
商売も人生も、誠実さと記録の積み重ねで成り立つ。
そんな古き良き日本の金融教育の精神を、現代の「おこづかい教育」にも生かしていきたいですね。