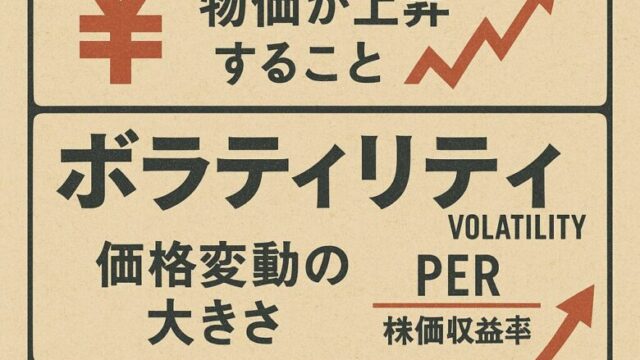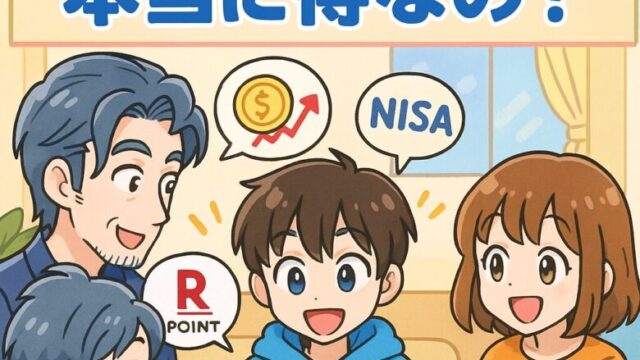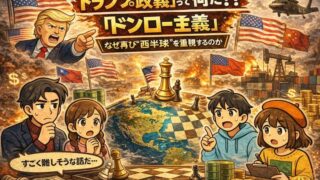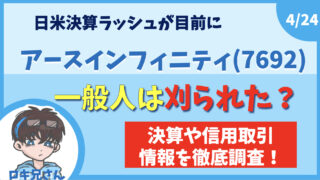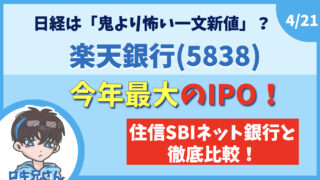目次
1. 相続税とは?
相続税とは、亡くなった方(被相続人)が残した財産を家族などの相続人が受け取る際に課税される税金です。
対象は現金や預金だけではなく、不動産・有価証券・保険金・美術品・借地権など幅広い資産に及びます。
相続税は「財産の総額」と「相続人の人数」に応じて課税額が変わります。つまり、家族構成と資産の種類が大きなカギになるのです。
2. 基礎控除の考え方と計算式
相続税がかかるかどうかは、まず「基礎控除」を差し引いてから判断します。
計算式
3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
例:相続人が「配偶者+子2人」の場合
3,000万円 +(600万円 × 3人)= 4,800万円
つまり、遺産総額が4,800万円までは相続税がかかりません。
3. 相続税率(速算表:2025年版)
基礎控除を超えた部分に対しては、以下の速算表で計算します。
| 課税価格(各人の取得金額) | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | 0円 |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
これは「超過累進課税」方式。つまり、財産が大きいほど高い税率がかかる仕組みです。
計算例
遺産総額が4,000万円の場合:
4,000万円 × 20% − 200万円 = 600万円
4. 計算の流れをステップごとに解説
相続税の計算は以下の流れで進みます。
Step1. 遺産総額を算出
現金・不動産・株式・保険などを評価額で合算。そこから「葬儀費用」「借金」などを差し引きます。
Step2. 基礎控除を引く
遺産総額 − 基礎控除額 = 課税遺産総額
Step3. 法定相続分で分割する
課税遺産総額を法定相続人ごとに割り振り。
Step4. 税率を当てはめる
速算表を使い、各人の取得金額に応じて税額を計算。
Step5. 特例や控除を適用
配偶者控除や小規模宅地特例などを反映し、最終的な納税額を確定します。
5. 特例・控除の活用法
相続税には、負担を軽減できる制度がいくつかあります。
配偶者控除
「1億6,000万円」または「法定相続分」まで非課税。小規模宅地の特例
自宅や事業用宅地の評価額を最大80%減額可能(条件あり)。未成年者控除
未成年の相続人は成人になるまでの年数×10万円が控除。障害者控除
85歳までの年数×10万円(特別障害者は20万円)が控除。贈与との併用
毎年110万円までの贈与は非課税。計画的に生前贈与と組み合わせることで、相続税の負担を抑えることができます。
6. 注意点と早めの対策ポイント
現金だけでなく、不動産・株式・保険も対象
資産が「現金化しにくい」形で残ると、納税資金の確保が難しくなる。最高税率は55%
世界的に見ても高水準。資産規模が大きい人ほど、早めの対策が必須。遺産分割でトラブルが発生しやすい
「誰がどの財産を受け取るか」を決めるのは感情的にも大変。遺言や事前の話し合いが重要。専門家相談の活用
相続税は計算や評価が複雑。税理士や司法書士に早めに相談すると安心です。
まとめ|家族と資産を守るための相続準備
相続税は 「基礎控除」→「速算表」→「特例適用」 の流れで計算。
配偶者控除・小規模宅地の特例・贈与の活用 が節税のポイント。
相続財産は現金に限らず幅広い資産が対象。納税資金の準備も重要。
家族構成や財産状況に応じて、早めの対策と専門家相談が不可欠。