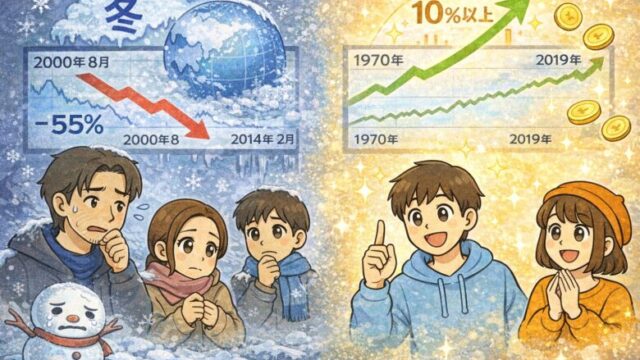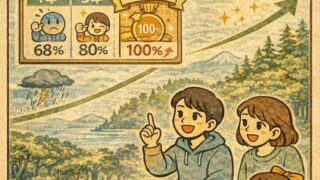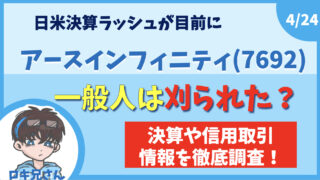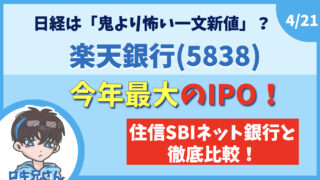目次
「ねぇ、お金ってどうやってできてるの?」
こんにちは。『えすふぁみ☆家族で株投資』へようこそ。
水曜日は“お金にまつわる疑問”をテーマに、ふだん見慣れたものをちょっと違う目線で考える時間です。
ある日、スーパー帰りにこんな会話がありました。
「お金の正体」ってなんだろう?
ふだん何気なく使っているお金ですが、その“正体”について考えたことはあるでしょうか。
紙幣は紙、硬貨は金属。ですが、それ自体の素材の値段は意外と安いのです。
たとえば、1万円札の製造原価はおよそ20円前後、500円玉も30円程度。
それでも1万円札は、全国どこでも「1万円の価値」として使えます。
なぜでしょうか?
それは、国(日本銀行)が「これは1万円です」と保証しているからです。
つまり、お金とは「信用のもとに動く道具」であり、「みんなが信じているからこそ価値がある」仕組みなのです。
お金を作っているのは誰?
日本のお金は、国家によって管理・発行されています。
紙幣(お札)は「国立印刷局」という機関で作られます。これは政府の管轄です。一方、硬貨(コイン)は「造幣局」という施設で作られています。こちらも国の組織です。
そして、これらのお金を実際に“発行する”のは、「日本銀行」という特別な銀行です。
日本銀行は私たちがふだん使っている“都市銀行”や“地方銀行”とは違い、日本にひとつしかない中央銀行。日本の経済を裏側から支える存在です。
お札やコインにはどんな工夫があるの?
今日は「観察実験」のような気持ちで、お札や硬貨を手に取ってみましょう。
まず、お札の色や人物が金額ごとに違うことに気づきます。
たとえば、1万円札には渋沢栄一、5000円札には津田梅子、1000円札には北里柴三郎が描かれています。色合いもそれぞれ異なります。
また、よく見ると模様に「日本らしさ」があります。
例えば、稲や桜、水流模様などが丁寧に施されています。
透かしやマイクロ文字など、見えにくい工夫もたくさんあります。これは“偽造を防ぐため”の技術です。
硬貨もよく観察すると、重さ・表面の手触り・彫りの深さなどが異なります。
500円玉は非常に複雑な構造をしており、偽造対策として“二色三層構造”と呼ばれる特殊な金属の組み合わせが使われています。
なぜ“勝手にお金を作っちゃいけない”のか?
まさにその通りです。
お金というのは「価値」そのものではなく、「みんなが信じている価値の象徴」にすぎません。
それを勝手に作ってしまえば、社会全体の“お金への信頼”が崩れてしまいます。
だからこそ、国が厳しく管理し、簡単にコピーできないように高度な印刷技術が使われているのです。
「お金=価値+信用+仕組み」
今回の話をまとめると、次のようになります。
・お金はただの紙や金属ではなく、国家が「これは○○円です」と信用を保証している道具
・紙幣は国立印刷局、硬貨は造幣局、日本銀行が発行を管理する
・偽造されないようにするために、すかし、特殊インク、手触り、材質など多くの工夫が詰まっている
・お金の価値は「素材」ではなく、「社会的な信頼」によって成り立っている
まとめ:見慣れたお金に、もう一度目を向けてみよう
【今日のお金にまつわる疑問】
お金は、国家の信用と技術によって守られている。
見て、触れて、考えて――「しくみ」に目を向けることが、未来の“おかね力”を育てます。