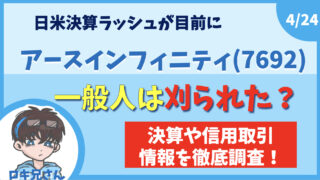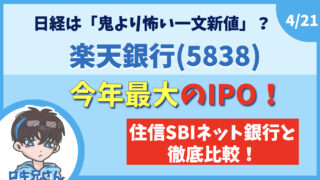目次
絵本で学ぶ“お金のほんとう”
こんにちは、『えすふぁみ☆家族で株投資』です。
土曜日は「子どもとお金」をテーマにしています。今回は「絵本を通じて学ぶお金のこと」。
絵本には、子どもにお金の価値や役割を“体験するように”伝える工夫がたくさん詰まっています。
1. お金を「選ぶ」「使う」を知る
絵本『おかねをつかう!』では、主人公が欲しい物を買うために「別の何かを買わない」という選択を迫られます.
このストーリーは、「お金は有限である」「何かを得るためには何かを諦める」という現実を子どもに自然に理解させます。
また、『100円たんけん』では商店街を歩きながら、同じ100円でも買えるものが違うことに驚く主人公。子どもは「値段と価値の違い」を目で見て学び、「自分の選び方で満足度が変わる」ことを体感できます。
2. 経済の流れを物語で理解する
お金の学びは「使う」だけではありません。
『レモンをお金に変える法』は、レモンを作り、売って、お金に変えるプロセスを描いた絵本。原価、価格、利益、市場など、一見むずかしい経済の仕組みを物語で楽しく学べます。
さらに『ありがとうかね』では、「人の役に立つことが仕事になり、その対価としてお金をもらえる」という根本的な原理をやさしく表現。
子どもは「働くこと」と「お金」がつながっていることを実感できます。
3. 貯金や投資を物語で伝える
お金を“使う”だけでなく、“貯める”や“増やす”視点も絵本から学べます。
『ポーチとピース-とうしについてかんがえるえほん』では、森の動物たちが「全部食べてしまう」か「一部を育てて増やす」かを選択する物語。
これは「複利の力」や「投資の重要性」を子どもに伝える、穏やかでわかりやすい教材です。
また、『かあさんのいす』は、家族の夢をかなえるために少しずつお金を貯めるストーリー。貯金の意味や、目標に向かって計画的に積み立てる喜びを実感できます。
4. 哲学的な視点からのお金
最後に、『買い物絵本』は少しユニークなアプローチをします。
「お金で買えるのは物だけ?」という問いから始まり、「気持ち」「時間」「体験」といった目に見えない価値に気づかせてくれるのです。
これは子どもだけでなく大人にとっても、「お金の意味」を再考するきっかけになります。
5. 絵本で学ぶ“お金の本質”
絵本を通じて学べることは実に多彩です。
選ぶ楽しさと有限性(『おかねをつかう!』『100円たんけん』)
経済の循環(『レモンをお金に変える法』『ありがとうかね』)
貯金や投資の大切さ(『ポーチとピース』『かあさんのいす』)
お金の哲学的な意味(『買い物絵本』)
まとめ
絵本は、お金を「知識」ではなく「体験」として伝える最高の教材です。選ぶ、使う、貯める、増やす、そして考える…。子どもにとって一番身近で楽しい方法で、お金の本質を学べます。